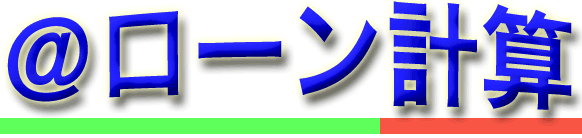仲介手数料の意味を分かりやすく解説
仲介手数料とは?
不動産取引において仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)とは、不動産の売買取引を行う際に売主、及び買主が宅建業者である不動産会社へ支払う手数料を言います。宅建業法により仲介手数料の上限が定められています。実例を挙げながら、不動産売買・交換を行う際の仲介手数料の計算方法について解説します。
なお、不動産会社が不動産所有者である場合など、「売主から直接不動産を購入する場合」は仲介手数料はかかりません。
仲介手数料の計算式
宅建業法により、仲介手数料の上限金額が次の通り定められています。法律で定められているのは仲介手数料の「上限金額」のため、不動産業者によっては仲介手数料半額や仲介手数料無料の業者も存在します。
不動産売買・交換の仲介手数料 計算式
仲介手数料の計算式は、不動産の取引価格の税抜き価格に対して次の通りです。
| 取引価格(税抜き) | 仲介手数料の計算式(税別) |
|---|---|
| 200万円以下 | 取引金額(税抜き)×5% |
| 200万円~400万円以下 | 取引金額(税抜き)×4%+2万円(税別) |
| 400万円以上 | 取引金額(税抜き)×3%+6万円(税別) |
不動産取引価格から消費税を除いた税抜き価格で上記計算式の通りに仲介手数料を計算します。実際に不動産会社に支払う仲介手数料は上記計算結果に消費税額を加えた価格となります。
仲介手数料計算の実例
それでは、仲介手数料の実例について実際の取引例を用いて計算してみましょう。
中古マンションを3000万円で取得した場合の仲介手数料の計算例は次の通りです。
仲介手数料計算の実例:取引価格のうち、土地代(非課税)と建物代(税込)に分けて計算します
一般的に不動産の取引は税込み価格で行われます。マンション価格3000万円と表示されている場合は、税込み価格が3000万円という意味です。仲介手数料は取引価格の税抜き価格を元に計算するため、不動産価格のうち非課税である土地の価格(非課税)と課税である建物価格(税込)の税抜き価格の合計額に対して計算します。
中古マンション3000万円のうち
土地代が800万円(非課税)
建物代が2200万円(税込)とします。
通常は、売買契約書に土地代、建物代の内訳が書かれています。購入前でしたら土地代と建物代のそれぞれを不動産会社に確認してみてください。個人が所有する不動産を取得する際は売主が土地代、建物代の内訳を意識していない場合もあります。
取引完了後に土地代と建物代の内訳を知りたい場合は、仲介手数料から土地代、建物代の内訳を計算する方法もあります。
仲介手数料計算の実例:不動産価格の税抜き価格を計算します
令和元年10月1日以降の取引(消費税料率=10%)の場合、上記例で不動産価格の税抜き価格は次の通りとなります。
土地価格800万円(非課税)の税抜き価格は800万円(税抜き)
建物価格2200万円(税込)の税抜き価格は2200÷110%=2000万円(税抜き)
上記から、今回取引の不動産の税抜き価格の合計額は
土地価格(税抜き)+建物価格(税抜き)
=800万円+2000万円=2800万円(税抜き)
となります。土地取引は非課税となりますので土地価格(非課税)=土地価格(税抜き価格)となります。なお、土地のみの取引の場合は取引価格の全額が非課税=税抜き価格となります。
仲介手数料計算の実例:不動産価格の税抜き価格から、仲介手数料を計算します
上記計算結果の不動産価格の税抜き価格と仲介手数料の計算式を使って仲介手数料を計算します。今回取引の不動産の税抜き価格は2800万円ですので仲介手数料は次の計算式となります。
仲介手数料(税別) = 取引金額(税抜き) × 3% + 6万円(税別)
= 2800万円(税抜き) × 3% + 6万円(税別)
= 84万円 + 6万円
= 90万円(税別)
実際の仲介手数料は別途消費税10%(令和元年10月1日以降の場合)がかかりますので、
仲介手数料(税込) = 90万円(税別) + 消費税10%
= 90万円(税別) + 9万円(消費税10%分)=99万円(税込)
となります。上記は取引価格のうち、土地代(非課税分)、建物代(課税分)の内訳が分かる場合の仲介手数料 計算式です。不動産売買契約書に土地代、建物代の内訳が記載されていない場合は不動産会社によっては不動産価格全体(上記例では3000万円)に対して仲介手数料を計算することもあります。不動産価格全体(上記例では3000万円)で仲介手数料を計算すると次の通りとなります。
仲介手数料(税別) = 取引金額(税抜き) × 3% + 6万円(税別)
= 3000万円(税抜き) × 3% + 6万円(税別)
= 90万円 + 6万円
= 96万円(税別)
仲介手数料(税込) = 96万円(税別) + 消費税10%
= 96万円(税別) + 9万6000円(消費税10%分)=105万6000円(税込)
上記の通り、土地代800万円(非課税)、建物代2200万円(税込)に分けて計算した場合と比べると仲介手数料が6万6000円も高額になってしまいます。不動産会社担当者の知識不足により不動産価格(税込)に対して仲介手数料を請求される場合もありますが、これは仲介手数料の払いすぎとなりますのでのご注意ください。
仲介手数料から土地代、建物代の内訳を計算する方法
仲介手数料から土地代、建物代の内訳を計算する方法を分かりやすく解説します。不動産取引後、または取引中に不動産価格と仲介手数料額が分かっている場合は次の手順で土地代、建物代の内訳を計算することができます。
仲介手数料の税別額を計算する
例えば
不動産価格(税込) = 5000万円(税込)
仲介手数料(税込) = 161万7000円(税込)
の時、仲介手数料の税別額は、消費税率10%(令和元年10月1日以降取引)の場合、
仲介手数料(税別) = 161万7000円(税込) ÷ 110% = 147万円(税別)
となります。
不動産価格の税抜き価格を計算する
上記仲介手数料(税別)を用いて不動産価格の税抜き価格を計算すると、
仲介手数料(税別) = 取引金額(税抜き) × 3% + 6万円(税別)
147万円(税別) = 取引金額(税抜き) × 3% + 6万円(税別)
取引金額(税抜き) × 3% = 147万円(税別) ー 6万円(税別)
取引金額(税抜き) × 3% = 141万円(税別)
取引金額(税抜き) = 141万円(税別) ÷ 3% = 4700万円(税抜き)
上記の通り、不動産価格の税抜き価格は4700万円(税抜き)であることが分かりました。
建物代にかかる消費税額を計算する
次に、建物代にかかる消費税額を計算します。
取引金額(税抜き) = 土地代(非課税) + 建物代(税抜き)
取引金額(税込) = 土地代(非課税) + 建物代(税抜き)+ 建物代にかかる消費税額
の計算式になるので
4700万円(税抜き) = 土地代(非課税) + 建物代(税抜き)
5000万円(税込) = 土地代(非課税) + 建物代(税抜き)+ 建物代にかかる消費税額
つまり
建物代にかかる消費税額 = 5000万円(税込) ー 4700万円(税抜き) = 300万円
であることが分かりました。
建物代(税込)を計算する
建物代にかかる消費税額が300万円ということは、
建物代(税抜き)= 300万円 ÷ 10% = 3000万円
建物代(税込)= 3000万円 + 消費税300万円 = 3300万円
となります。
土地代(非課税)、建物代(税込)の内訳を計算する
以上から、土地代(非課税)は
土地代(非課税) = 5000万円(税込) ー 3300万円 = 1700万円
ですので、土地代(非課税)、建物代(税込)の内訳は
建物代(税込)= 3300万円
土地代(非課税) = 1700万円
であることが分かりました。
土地代(非課税)、建物代(税込)の内訳計算のまとめ
居住用の住宅を売買する際は建物代、土地代の内訳は特に意識しなくても問題ありませんが、投資用の不動産を売買する際は、税金の計算を行うために土地代、建物代の内訳が必要となります。
仲介手数料を安くする方法
数千万円~数億円の不動産を売買する場合、その仲介手数料は数十万円~数百万円になります。仲介手数料は法律で上限が決められているだけですので、交渉により、または仲介手数料が安い業者を通じて取引することにより、または仲介手数料の安い物件を取得・賃貸することにより仲介手数料を安くすることができます。または売主から直接不動産を取得する場合は仲介手数料はゼロ円となります。
仲介手数料の安い業者、営業マンを通じて取引する
特に不動産を賃貸契約する際は仲介手数料ゼロ円、仲介手数料半額などの業者が存在します。
同じ物件でも業者により仲介手数料が異なることがあるので、住みたい物件が決まっている場合は「物件名 仲介手数料」などのキーワードで仲介手数料の安い業者をグーグル検索してみましょう。
東京都内で不動産を購入する際、既に欲しい物件が決まっている場合、その不動産が複数の不動産会社から購入できる場合は仲介手数料の安い不動産営業マンを紹介できる場合があります(概ね3000万円以上の物件)。ご意見・ご要望コーナーから「物件詳細、SUUMOもなどの物件URLなど。仲介手数料値引き業者紹介希望」と記載してお送りください。
仲介手数料の安い物件を取引する
特に不動産を賃貸契約する際は仲介手数料ゼロ円、仲介手数料半額などの安い物件が多数存在します。仲介手数料ゼロ円のからくりは、不動産オーナーが早く入居者を決めたいために広告料を不動産会社に支払う契約になっていることがあります。
仲介手数料を交渉する
交渉するだけなら無料です。不動産を取引する最中、取得するかどうかまだ迷っている段階なら担当の不動産営業マンに交渉してみてください。
売主から直接不動産を取得する
売主から直接不動産を取得する場合は仲介手数料は発生しません。同じ物件でも売主が直接販売している場合は仲介手数料はかかりませんので既に欲しい物件、住みたい物件が決まっている場合は売主が直接販売していないかネットで検索してみてください。
お役立ち情報
最新情報
2025/9/1更新 ARUHI フラット35レビュー 9月実行金利を掲載 (Web割引あり)
2021/8/18 プライバシーポリシーを分かりやすい位置に設置しました
2020/5/11 金融機関別、住宅ローン返済困難者支援のまとめ(新型コロナ対策)
2019/8/17 住宅ローン 控除 計算、消費税増税後の控除期間13年に対応
2019/4/15 フラット35のメリット、デメリット
2019/4/10 カードローン 計算式
2019/4/5 フラット35 年齢制限、年齢による借入可能年数
2018/9/5 キャッシングシミュレーションで6回払い20回払いなど、1年単位以外のローン計算可能に。
2018/8/16 繰上返済計算がより分かりやすい結果表示になりました。
2018/8/5 金融電卓 おすすめ購入ガイド
2018/8/3 住宅ローン 控除 計算
2018/7/25 フラット35特集
2018/3/28 住宅ローン 返済額 早見表で金利比較できるようになりました。
2018/3/25 借入可能額額計算できるようになりました。
2018/3/21 返済予定表ページで月次、年次切替できるようになりました。